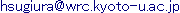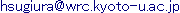
| 京都大学野生動物研究センター>屋久島フィールドワーク講座>第9回・2007年の活動−人と自然班−感想文 |
| 概要 | 人と自然班 | サル班 | シカ班 | 植物班 | 公開講座 | スタッフ |
| 報告書 | 感想 |
今回のFW講座で、私は初めて屋久島を訪れました。FW講座がなければずっと行くこともなかったかもしれません。それほど屋久島は私にとって遠い、意識の外にある存在でした。私は東京で生まれ、旅行以外で東京を離れたことはありません。だから、屋久島を訪れる前は、島の人たちの生活はほとんど想像がつきませんでした。「コンビニがなくて不便そう、憧れもするけれど、実際に生活するのは私には無理かもしれない・・・。」その程度の認識しかありませんでした。
今思うと、我ながら浅はかな考えです。コンビニがそんなに大事なのか、と問われてもしかたない。東京という町がいかに私の視野をせばめていたかがよくわかります。屋久島での体験は、自分が価値観でしかものごとを見られていなかったことを痛感するいい機会になりました。屋久島で出会った人々、景色、そこかしこにいる動物たち。すべてのものが新鮮で、東京にはないものでした。その中でも特に印象に残ったものをいくつか書き記しておきたいと思います。
まず私が驚いたのは、屋久島の人々の政治意識の高さです。屋久島には東京よりずっと、地方自治の精神が育っていました。永田の人の多くが、地域の行政に大きな関心を寄せるだけでなく、地域の住民が積極的に町の将来を考えている。加えて、永田の人たちは雄弁家です。まさに一人一人が永田の将来を見つめ、そして昼夜議論しあう、そういった力強い気概が永田を取り巻いているようでした。東京ではまず考えられないことです。
私は大学では政治学を専攻していますが、国民の政治参加意欲というのは大きな研究テーマのひとつです。民主主義において国民の積極的な政治参加は何よりも重要な要素ですが、日本人というのはどうも権威主義的な国民性で、あまり地域議会の活動に関心を示さない。けれど、そういったものは法律や行政でどうこうできるものではなく、その地域に生きる人々の参加意欲が重要になってくるものです。東京にいると、残念ながらその意欲を感じることは困難です。だから大学で勉強をしていても、日本人の国民性というのは所詮変えられないのだというネガティブな捉え方から抜け出せずにいました。
しかし、今回永田で感じてきたのは、まさにそういった地域のパワーでした。実際にそういった気概が日本に存在していること、そしてそのパワーを実体験として感じられたことは、私を大いに勇気付けました。
その背景にあるのは、深い郷土愛と地元への誇りです。郷土への愛、先祖代々受け継がれてきた土地への誇りが、永田の人々と話しているだけで伝わってきました。永田の人々は本当に気持ちを言葉にするのがうまい。永田の人々の話を聞いていると、自分が忘れていた何か大事なことを思い出せるような気がしてくるのでした。それはきっと、人間なら誰もが持っている当たり前の感情です。人の気持ちを考えるとか、お年寄りを尊敬するとか、自分の正義を貫くとか、そういったことだと思います。日本人としてこうありたいと思うような道徳感を守り、実行すること。昔はあった気がするのに、今の自分たちには欠けているように感じるものが、屋久島ではまだ残っている気がしました。永田の人々は地元を誇りに思い、そしてそこにいる人々を大事にしているのがわかります。だから、永田の人々の屋久島への思い、そして子供たちへの思いを話していただけた時は心から感動しました。
屋久島での風景もまた、感動的でした。特に屋久島で見た夕日は忘れられません。今までの中で一番壮大な景色です。沈んでいく太陽と海を見ているだけで、地球を感じることができました。夕日を見るだけで自然の壮大さや、自分が自然の中で生きていること、同時に自分がすごく小さな存在であること、小さいなりに何かやれるのではないかという気持ち・・・とにかくいろんな気持ちが押し寄せてきて、今日に感謝し、明日もがんばろうと思う。我ながら不思議なことを言っていると思いますが、あえて言うならそういう感覚です。これも、都会ではちょっと出来ない、素晴らしい体験でした。自然の神秘的な力を肌で感じてきてしまいました。
屋久島では本当に貴重な体験ができたと思っています。今まで書いたどれもが、都会では絶対に体験出来なかったことでしょう。私がFWに参加したことで、屋久島の人々から学んだことは数多くあります。私はこのさきも東京に住んでいるでしょうが、東京にないものを知ることで、私の東京生活も変わって行けるだろうと思います。屋久島で学んできた郷土愛の精神、人の暖かさを忘れずに東京と向き合っていきたいです。また、そういった機会を私にくれた屋久島に愛着を感じることで、東京中心の考え方を払拭できるいい機会になりました。あの雄大な自然を東京の中に見つけることは不可能なので、折々でまたあの自然を感じに屋久島を訪れられたらと思います。
永田のみなさん、お元気ですか。
屋久島フィールドワーク講座中は、聞き取り調査を中心に大変お世話になりました。
最初に永田地区に行って驚いたことは、永田の人々が大変に元気で、話好きで、そして全くよそ者の私たちに心をオープンにしてお話を聞かせてくださったことです。それに由来するのだと思いますが、丸橋先生は永田集落のことを「永田大学」と言っていらっしゃいました。確かにその通りだなと思いました。(永田の人々のお話は退屈な大学の授業より興味が持てた、というのも理由の一つですが。)永田の人々は「永田大学」の教授として、理論的にかめんこ制度の詳細についてお話をしてくださいました。もともとはかめんこ制度が複式学級の解消を目的として始められたこと、それを支える永田の人々のエネルギーや教育への高い関心、またかめんこを受け入れていらっしゃる里親たちの愛情、それらすべてがかめんこや永田の子どもたち、しいては未来の子どもたちを思ってのことだと知りました。この制度を支えているのはやはり永田地区の人々が子どもたちに常日頃から目を掛け、気配りをしているからだということがわかりました。「人の子も わが子も同じ 永田の子」というスローガンは、それだけが一人歩きするのではなく、確実に内実をともなってこの地域で達成されているなということを感じました。
里親たちのお話を聞いていて、まなざしが非常にあたたかいことに驚きました。時にかめんこの両親や子どもたちは病気や非行を面接のときに隠すことがあっても、それを理解し、かめんこと正面から向き合っている里親たちの姿勢に感動しました。世の中ではネグレクトや子どもに対する虐待が叫ばれて久しいのに、永田ではそれとは全く逆行した動きが進んでいると思いました。そしてそれは子育ての根本に回帰するものだということを教わりました。
また永田の子どもたちは、大変たくましく遊んでいました。川は流れが速く、海も流れを持っている。山は険しく、天気はころころ変わる。こんな環境で遊んでいれば自然と子どもはたくましくなるだろうなと思いました。子どもたちは危険な場所を自分たちで教えあいながら冒険に出かけていくようでしたが、そこには必ず大人の目がちゃんとあることが伺えました。子どもは大人が見ていると安心して行動範囲を広げられると言われますが、永田では大人の目がちゃんと行き届いていて、それらが永田の子どもたちの遊び場の多さを提供しているのだと感じました。
実は私は永田に来るまで少し永田の子どもたちをかわいそうに思っていました。永田は屋久島の西の端にあり、飛行場や港から遠く、交通は不便なところです。そして集落も三方を山に囲まれ、目の前は黒潮が流れています。私はこの土地の子どもたちの世界が狭く、そしてそのことが経験や将来の可能性を狭めているのではないかと思っていました。しかし、それは間違っていました。調査の途中で永田の子どもたちは集落から見える海の先を見ている、というお言葉を聞いてはっとしました。海は世界とつながっているという地理的なことはもちろん、かめんこ制度によって全国から来る子どもたちによって外の世界を知り、そして彼らとの交流をかめんこの期間が終わっても続けることでさらに視野を広げているのだということに気づきました。
もちろんかめんこだって永田にいる数年間でたくさんのことを吸収していきます。それは永田の自然環境の良さだけではなく、子どもが物事に敏感で刺激を受けやすいということがうまく合わさって生んでいる効果なのではないでしょうか。少子化が進んだ都会では大人が子どもに手を貸し過ぎ、そして可能性や行動範囲を制限するということが起きています。永田というフィールドの中で自然とふれあい、いろいろな人と出会うことは、人間的な成長をかめんこにもたらしているのではないかと考えられます。
最後に、私は現在大学で地理学を専攻していて都市と農村の比較をしているのですが、過疎は結局打開できないというのが私の今までの考えでした。人口が減れば負のスパイラルに陥って結局その地域は再生しないと思っていました。それは私の出身地の福井県の田舎がそうであったのも起因しています。しかし、永田地区は過疎との闘いをずっとしています。かめんこ制度はもう10年も続いています。それは亀の歩みではあるかもしれないけれど、確実な一歩ではないかと思います。短期的では見られない効果が、10年後、20年後に現れることを期待しています。そしてこの制度が屋久島、そして日本の過疎地域で受け入れられるようになれば、私は日本の過疎の社会に、日本の教育に変化が見られるのではないかと思います。
お話を聞かせてくださった永田集落のみなさん、そして1週間一緒に活動した丸橋先生、チューターの松原さん、そしてヒト班の石山さん、上敷領くん、久保さんには大変お世話になりました。たくさんのことを考えることのできる講座であったと思います。本当にありがとうございました。
私の住んでいる鹿児島県内の小学校の半数以上が僻地といわれています。しかし、私は僻地の学校の現状をあまり知りませんでした。また友達が一年間山村留学したことがあったので、そういう制度があることは知っていましたが、それぞれ募集している場所でネーミングが異なり、事業内容も様々であることを今回初めて知りました。鹿児島の教育現状を知るいい機会と思い私はヒト班を希望し、永田に1週間のかめんこ留学をさせていただきました。
今回、一番印象に残っている事は、初日にかめんこ留学という名前の由来について地元の中学生の男の子が教えてくれた言葉でした。『かめんこ留学のかめんこのは、亀の子どものことなんだ。ここ永田はね、日本で一番多くのウミガメが産卵する場所なんだよ。そしてここで生まれた子ガメたちはアメリカやメキシコまで行って、成長して親亀になって、また生まれ故郷の永田の浜に戻って来るんだ。だから、留学生にも、また永田に戻ってきて欲しいなという願いを込めてあるんだよ。』笑顔で話してくれた、その子の言葉に鳥肌が立つほど感動。また、次の日には校長先生のご好意により、ウミガメ放流という貴重な体験までさせていただきました。あんなに子ガメが出べそだなんて…という驚きつつ、中学生達と一緒に横一列に並んで放流。果てしない大海原に向かって、小さな小さな体で懸命に手足をばたつかせて挑んで行く姿は、なんとも弱々しく…無事に永田の浜辺に帰ってきてほしいと願わずにはいれなかった。
今回は突然のインタビューやお願いにも関わらず、多くの方々が協力してくださり、様々な視点から『かめんこ留学』について知る事ができました。どの立場の方にも永田地区から学校をなくさないという強い思いが根底にあることを知り、学校の存在って大事なんだなと思いました。いつもそこにあるのが当たり前のように感じてしまうもの、それはなくなるかも知れない、失うかもしれないと分かった時に人は途方にくれる。それは学校だったり、自然だったり…そこからの行動は人それぞれ。過疎という現状で、もう人数も少なくなったんだし、統廃合は仕方ないよね…時代の流れだしね。とそこで諦めるという道もなかった訳ではないと思う。しかし、永田の方たちは、学校がなくなったら寂しい、どうにかしようと思って地域主体の留学制度を始めた。この実行力はホントに素晴らしいものだと思うし、永田地区の財産のように思えました。永田を車で通ると『過疎が進んでいる』と聞いていましたが、家は部落ごとに密集しているし、あまり感じないなと思っていました。しかし、いざ道で会った方にインタビューしようと思って、路地を歩いてみると、全然人に出会わず、1時間近くブラブラするはめになってしまい、その時に人がいない!というのは強く感じました。かめんこ留学で子ども達がいる時と、夏休みでかめんこ達が帰ってしまうと、路地に子どもの声が聞こえなくなって寂しいよねとおしゃっていた方もいたので、かめんこの存在は大きいようです。もう学校に縁がなくなった方でも、かめんこの事は知っていて、里親になっていたりと学校存続のために活躍なさっていて、永田地区全体の教育に対する熱心な雰囲気を感じました。20年以上前からある「人の子も 我が子も 同じ永田の子」というスローガンも、この地区だからこそズット受け継がれているのでしょう。
かめんこ留学制度は私達がインタビューした子どもにもすごく影響している事も分かりました。毎年半数近くの学校の友達が替わるけれども、もう10年も続いているという事もあり、子ども達には受け入れ態勢というものが出来ていてすぐ友達になるし、この状況をしっかりと理解し楽しんでいるようでした。私は小学2年生の時に転校して新しい学校に来た時、一人女の子が声をかけてくれた事は今でもスゴク鮮明に覚えています。そんな声をかけてくれる子が永田にはたくさんいて、友達の輪がどんどん広がっていくんだろうなと感じました。私達が行ったときは夏休みで、去年の留学生が遊びに来ていた。留学生は永田での生活は居心地の良いものであったから、戻ってきたのだろう。永田の子は、僕達は全国に友達がいるんだよと嬉しそうに教えてくれました。永田の子ども達は屋久島という日本の南の島に住んでいながら、目は世界に向いていた。外から入ってくる色々な刺激に触れているからだろうなと思いました。
この1週間で、すっかり永田の人柄に触れ、土地の魅力に惹かれ、離れなくなりそうだなと感じています。屋久島に来る流れがあって、みんな屋久島に来ているんだろうなという話を丸橋先生として、笑ってしまいました。なぜか屋久島に呼ばれている気がするんです。根拠はありません。でも神秘の国(“・”を入れる)屋久島には、人を惹きつけて離さない力があるのは確かです…
現在、私は教育学部で小学校の先生を目指して勉強しています。教師という仕事は、子ども達より長く生きている分だけ自分の知っている事を子どもに教えて、子どもの成長を近くで見守る事ができる。と同時に、子ども達から色々な事を学んで自分自身も成長できると思うから。ここ永田では、地域の方にも育てていただけると感じました。ぜひこれからは、初任地永田という思いを胸に学校生活を過ごしていきたいです。
今回はボランティア係という立場での参加だったのですが、しっかりFWに参加させていただき大変申し訳なかったのですが…たくさんの事を考えさせる機会になりました。観光として訪れては知る事のできない屋久島を見る機会を与えてくださった全ての方に感謝いたします。本当にありがとうございました。
「屋久島でフィールドワークの研究を体験してみませんか?」そんな掲示をみたのは確か6月の初め頃だったと思う。たまたま用事があって訪れていた市外の別の大学の掲示板で、通りがかりに偶然目にしたのだ。「屋久島か、そういえば鹿児島に住んでいるのに一度も行ったことなかったなあ。フィールドワークっていうのもおもしろそうだし、応募してみようかな。」そう思って締め切り日をみてみると、あと一週間ほどしかない。ちょうど中間試験の勉強やレポート作成に追われている時期である。課題作文までは手が回らないだろうと一度はあきらめた。だが、なんとその日の晩、はしかが流行しているためうちの学部も明日から休みだという連絡が入ったのである。試験もレポートも延期、折良く急に時間の余裕ができたことに何か運命的なものを感じ、一気に4つの課題作文をしたためてメールで送った。
「人と自然」班を第一希望に選んだのは、フィールドワークを通して島の人々と深く触れ合えると思ったからである。理系学部なので調査テーマとしては、むしろサル、シカ、植物班の方に興味があったのだが、僕は昔から自分が興味のない方面に興味を持ってしまうという悪い癖があるので、こうした、社会学系の調査にもふれてみたいと思ったのである。
フィールドワークという調査技法自体、今まで経験したことがなかったので、苦労することや分からなくなることも多かった。だが新たな発見や驚きもあり、フィールドワークのおもしろさも味わうことのできた、貴重な一週間だったと思う。
調査の舞台となった永田地区は人口552人の小さな集落で、豊かな自然に囲まれた美しい所である。人々は皆、明るく親切で、何より話し上手。インタヴューの時もとても熱心に話してくれ、不慣れな自分にはとても助かった。苦労したのはメモの取り方。話をそのまま書き写すわけにもいかないので、内容をかいつまんで、要領よくまとめなければならない。どの情報が役に立つのか、その情報は何を意味しているのか、その場で素早く判断するのはとても難しかった。一見、何の関係もないような情報でも、後から見直してみると他の人からの情報とつながっていたり、何かの裏付けとなっていたりすることも多かった。どんな些細な情報でも、なるべくメモをとるように心がけたが、聞き漏らしや勘違いなどもあって、後からデータをまとめ上げる段階になって班のメンバーともめてしまうこともあった。また、インタヴューした人たちの立場や利害関係の違いなどから、インタヴューの内容に矛盾や食い違いが生じていることも多かった。誰の話が本当なのか、どの情報が実情に一番近いのか、まるで芥川の小説『藪の中』を読んでいるようで、もつれた糸を解きほどくように、それらの矛盾や食い違いを自分の中でうまく説明づけるのは大変だった。
インタヴューしているとき、メモをとっているときに新たな問題が浮かび上がってくることも多かった。それらの問題を秩序立てて整理し、つじつまが合うようにうまく組み立てていくと、根本となっている問題設定そのものも、それに合わせてうまく設定し直さなければならない。今まで研究というと簡単な実験や文献調査といったものしか経験してこなかった自分にとって、これは非常に奇妙な体験だった。目的や課題設定をはっきりさせてから調査をするのが当たり前だと思っていたのに、ここでは、調査をしてから目的や課題が浮かび上がってくるという、いわば、逆転の現象が起きていたのである。はじめは「うーん、こんなんでいいんだろうか」と疑問に思っていたが、後半になると、だんだんその出たとこ勝負的な姿勢にむしろフィールドワークの醍醐味を感じ始めていた。つまりはフィールドワークとは、まずは現場に入ってみて、そこにある人や物や生活を実際に体験してみよう、そうすることで課題や問題がだんだん見えてくるようになるはずだということなのである。
他にも苦労したこと、大変だったことはいっぱいあったが、それらはすべてフィールドワークとはいかなるものなのか、という事を教えてくれるよい材料になったと思う。それにフィールドワークを学ぶことを通して、いかに自分が現象に縛られ、物事の表面だけしか見ていないか、いかに物事の本質を捉えきれていないのか、ということを痛感させられた。そういう意味では、学問という活動の原点を味わうことができたと思う。実際、フィールドワークの手法をどれだけ身に付けることができたかといえば、おそらく少しも身に付いていないというのが実情だと思うが、今回の講座で自分は、単なる知識や体験以上のもの、今後の人生の糧となるものを得ることができたと思う。
屋久島に来る前は、お金や時間に追われて、結構、過酷な(?)日々を送っていた。正直に言うと、当座の資金の目途が立ったので今年の夏はどっかに遊びに行きたい、という旅行気分も大きかった。もっと正直に言うと講座の前日(当日?)もバイトという惨状だったので、いきなりはじめから少々バテ気味だったのだが、永田の浜辺で波と戯れたり、小学校の子供たちとドッジボールをしていると、なんだか心癒され、生きる力が湧いてくるようだった。特に永田からの帰りに見た夕日は本当に美しかった。
「また見つけた。
何を?
永遠。
太陽と溶け合った海のことさ。」
というランボーの詩の一節がぴったりだった。
実際にフィールドワークができたのは5日間という短い間だったが、期間中、永田集落のいろいろな人たちに出会い、お話を伺うことができて、観光で来ていたら絶対に味わうことができなかったようなとても貴重な体験ができた。丸橋先生が「永田の人たちはみんな自由人なんだよ」ということをおっしゃっていたが、本当にここの集落の人々はそれぞれが自分の考えを持ち、何にも束縛されずにのんびりと生活しているように感じられた。永田の人たちの素朴な生活や暮らしぶりに接していると、まるで人間の生活の原点が映し出されているようで、とても印象的だった。便利で裕福だが、いつも忙しさに追われている都会での生活と、不便で収入も少ないが、のんびりと心豊かに過ごすことができる田舎での暮らしはどちらが人間として幸福な生き方なのだろうかと、ふと考えさせられた。
中国の古典、「老子」の中には理想の国の形として、「小国寡民」という言葉がある。「国が小さくて住民が少なければ、人々は過剰な知識や欲を持たず、衣食住すべてに満足して、他の地域へも行きたいとは思わない。」という意味だ。講座期間中、永田に行くたびに、その言葉がいつも頭に浮かんでいた。
今回のフィールドワークでは全国からこの講座に参加した学生や先生方との出会いも大きな刺激になった。特に先生方は皆さん、それぞれの専門分野で長年、活躍されてこられた方々で、お話は大変参考になった。皆さん個性的でキャラの強い方々で、朝食や夕食のときに交わす取り留めのない会話もとても面白かった。機会があれば、今度は「屋久島に生息するフィールドワーク研究者の生態」なるフィールドワークも企画していただけたら面白いと思う。
最後に、この講座を主催していただいた上屋久町役場の皆さん、調査に協力していただいた永田の人々、いろいろとご指導いただいた先生方、そして一緒に頑張った仲間たち、すべての人々に感謝の意を述べ、僕のつたない感想を終わりたいと思う。一週間という短い間でしたけれども、とても楽しくて、貴重な体験が出来ました。本当にいろいろとありがとうございました。
丸橋が「人と自然」班の講師として、永田集落をフィールドとして活動するのは、2006年度が最初で、今回2007年度が第2回目となります。1973年に初めて屋久島を訪れてから、もう35年足らずになります。学生のレポートにありましたが、私にとっては、青春時代を過ごした場所であることよりも「大学」だったとの思いが強くあります。社会や人間について、本当の意味でリアリティーをもって考え対処していく手がかりを得た場所でした。つまり、沢山の人間と出会い、語りあった場所だったということです。豊かな、心に残る出会いを、より意義あるものにしてくれたのが永田を取り巻く自然環境であったことはいうまでもありません。
フィールドワークのモットーは「目から鱗」という言葉でしょう。人と出会い、人が語り出す言葉によって「目から鱗」が剥げ落ちるように感じることができるのが、フィールドワークの醍醐味でしょう。人は、偏見に満ち溢れているものだと実感し、謙虚に人々の言葉に耳を澄ますことができるようになりたいものです。こうした「目から鱗」の体験をしたことが、学生のレポートの端々に感じられるのは、講師としてうれしく思います。永田に最初に訪れた頃と比べて、だんだんと通い慣れた場所となり、心が変化し、態度も変化していったことを読みとれます。欲を言うと、この屋久島フィールド講座の活動の成果として、すべての参加者が、これから出会ういかなる事柄にも、自らが鱗を目から剥ぎ落とすような、心と世界との関わりを創りだしていって欲しいと願っています。
昨年度は、こども時代の遊びを男女、3世代にわたって聞き、屋久島永田の自然や社会の変化と遊びの変化との関係を探るというテーマを設けました。学生レポートの結論にもありましたが「こども時代は、いつも楽しい」と素直に感じ取れる永田集落での聞き取りでした。ひるがえって、大都会のこどもたちの息苦しさを思うとき、環境のもつ意味はやはり重要です。今年は、夕陽を見る機会を毎日設けるように、意図的に努力してみました。大地と空と海と宇宙とが出会う瞬間を何度もみることを経験して欲しかったのです。雄大な景色と劇的な時間の変化は、心を洗ってくれるものです。
フィールドワークに準備不足はありがちなことです。過不足無い準備よりも「出たとこ勝負」とでもいうべき底力を、若い時代には身につけるようにと願っています。その勝負を支えているのが語る力であり、永田の方々が「こどもとでも、話せばわかる、わかりあえるまで話し合う」という揺るぎ無い信念を学生に伝えてくださったことを本当に感謝いたします。
私は1995年から西部林道でサルの調査を始め、ちょうど今年で干支がひと回りしました。当時、浜町の町営住宅にお住まいの田畑裕子教頭先生とそのお母様に大変お世話になり、このお二方を通じて永田の運動会(とその後の飲ん方)に参加し、みかん山でポンカン収穫や除草のお手伝いをささやかにさせていただいたり、美味しい手作りお惣菜や野菜を頂いたりと、永田の方々に支えられた幸せな調査生活を送ることができました。田畑先生には今回のテーマに「かめんこ留学」を選ぶきっかけと足場をいただきましたことを感謝しています。
昨年のFW講座から、私がお世話になった屋久島の素晴らしさを若い学生に伝える機会を得てサルとシカの調査方法を教え、今年は丸橋先生から永田での人類学調査を教える助っ人にとお声をかけていただきました。丸橋先生の世代と永田の方々との深いお付き合いは、私たちの世代に古き良き時代の伝説のように口伝されていましたが、私はそこまで豪放磊落なお付き合いまで至っていませんでしたので、当初は何を教えたら良いものかと少々戸惑いを覚えていました。
しかし、さすがは丸橋先生たちを育てた“永田大学”。「かめんこ留学」に関わる大人も子どもも大変議論上手で、ひとりひとりが確固たる意見を情熱的に語る力にみなぎっています。永田の方々の話に飲まれ気味だった学生たちも永田の方々に日々感化されてか、次第にインタビューで積極的に発言するようになっていきました。「かめんこ留学」について学ぶと同時に、かめんこさんのように永田の方々に育ててもらう姿を見てながら、私も学生同様に永田の方々から人に教える心の大切さを学ばせて頂きました。どの方の話もおもしろく、サル調査をしていた時にもっと永田の方々と飲む機会を作れば良かったと大変残念に思いました。
永田の方々の堂々と相手と向き合って話し合う姿勢の根元には、相手への思いやりと信頼が息づいているようにみられました。この素晴らしい気質は都市の教育環境では残念ながら不足しがちで、そのような環境にいる子どもは発言することを怖れ、他者の言葉に怯えるようになります。しかし、世間の荒波への自己保身を覚えるのは小中学生(大学生も)には早過ぎ、それより話し合いをあきらめない心根の強さと相手を思いやる心、それらを安心して身につけられる教育環境が子どもたちには必要です。その実績がある永田の社会・自然環境の重要性と必要性は、今後も増していくことになると思います。かめんこ留学を支える永田と屋久島の将来を考えるすべての方々に尊敬と感謝をもって、学生さん共々学んだ事を将来に活かすことを願っています。
京都大学野生動物研究センター > 屋久島フィールドワーク講座 > 第9回 2007年の活動−人と自然班−参加学生レポート
このページの問い合わせ先:京都大学野生動物研究センター 杉浦秀樹