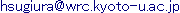図1 調査地の地図。発見した古道、人工物と調査ルートを記した。
| 京都大学野生動物研究センター > 屋久島フィールドワーク講座 > 第7回・2005年の活動-サル班-報告書 | 最終更新日:2005年12月17日 |
| 概要 | 人と自然班 | サル班 | シダ班 | ヤモリ班 | 公開講座 |
| 報告書 | 写真集 | 感想 |
参加者:久保奈都紀、関加奈子、長谷川大也、若松裕紀
講師:杉浦秀樹・田中俊明
サル班は初日から三日間、1960年代まで人が住んでいたといわれる川原地区周辺の古道を探しました。この古道は現在の西部林道が出来る前に住んでいた人が利用していたと思われる道です。私たちは古道を探すことによって、川原地区に住んでいた人達の生活様式を調べることや、後に行ったサル・シカのラインセンサス法による密度調査のための調査ルートを作ることが出来ました。西部林道はアスファルトの道であり、道の周りには木も少なくなっています。このような道では、夏には暑くなり、冬は冷たくなるため、この地域の中ではやや特殊な場所だと考えられます。それに比べて森の中にある古道は森と一体化した場所としてよいでしょう。この道を調査に利用することによって、よりよい結果が得られるのではないだろうか、と考えました。
川原地区周辺の森の中で見つけた古道で、1~2mの広さで木が生えていない部分があり(生えていてもまだ幼い細い木)、先まで一本道が続いている、平らで歩きやすい道のところもありました。昔の人が歩きやすいように伐採して道切り開いていたのではないかと思われました。獣道もシカが何度も同じ道を通ることで平らにはなりますが、道幅がとても狭いので、このような古道とは区別できます。
また、この古道の周辺には数々の人造物を発見することが出来ました。例えば「石組み」です。これは急な斜面を削って平らにした部分の側面に2、3段ぐらいずつ石が積み重ねてあって、道を補強していました。石組みの積み方を見てみると分かりますが、とても天然で積み立てられるような感じではありません。様々な気候条件に耐えうる道にするために、組み立てられたのでしょう。このことからも、この古道が昔の人がいかに大事に利用していたのかが伺えます。「炭焼き釜」もありました。大きいもので、直径が3.5mあり、形状は底の広い、おわん形でした。釜は石を積んで作ってありました。川原の集落の隣の半山の集落でも炭を作って、出荷していたという報告書もありました。川原でも大量の炭を作って運んでいたのかもしれません。そうならば、古道の横に炭焼き釜があるのは納得できます。
傾斜のすくない平坦な所は、きちんとした古道を確認することが出来ませんでした。しかし、何カ所かで陶器の皿やレンガ、焼酎のビンを見つけることが出来たので、ここに人の住んでいたという証拠となります。また生活用品を見つけた近くで、みかんの木や小さな竹やぶも見つけました。みかんは食料にするために、竹は生活の様々な場面に利用することが出来るので、人よって植えられたものとと考えられます。
昔、港があった場所も見つけることができました。山の中に比べると、海の方は、より劣化が激しかったですが、コンクリートで道が作ってある場所を見つけることが出来ました。海で魚をとって食べていたのではないでしょうか。また山の海沿いの道で、標高50mくらいの地点で幅50㎝ほどの古道も見つけました。平坦で、石組みも確認できたので古道と判断しました。この道もずっと続いていて、大きな岩のところでは岩が削ってあって人が通れるようにされていて、立派なものでした。時間がなくて途中で引き返してきたので、どこまで道が続くか気になるところです。
このような発見から、昔の人達も昼は港での漁業や畑での農作などをしていて、夜は焼酎を飲んで家族団欒して…日本人の変わらぬ生活の姿というものが見えた気がします。古道のおかげで、ラインセンサスのルートにしたことによって一定の速度で歩いて観察を行うことが、古道のない森付近を歩くときより容易にすることが出来ました。また道順も分かりやすく、森を歩くことに慣れていない受講生にとっては足元をあまり気にせず歩けて、周囲の動物の観察・調査に集中することができてよかったです。

図1 調査地の地図。発見した古道、人工物と調査ルートを記した。

図2 調査ルート。古道を利用して設定した。
シカの頭数とサルの群数を推定するために、ラインセンサス法を用いて調査をおこなった。
調査場所は、西部林道川原地区で、標高約50mの調査路と標高約100mの調査路、合計5キロメートルの調査路を設定した。この調査路を2班に分かれて、1日1回3日間(8月21日~23日)調査した。3日間合計14.3kmを歩いて調査した。
サル・シカを発見できるように、あたりを見まわしながらゆっくりと歩いた(平均1.4km/h)。サル・シカを発見した場合、以下の記録項目を記録した。
サルの場合は群れでいることが多いため、次々に個体が出てきた場合でも、最大観察時間は5分までとした。また、鳴き声しか聞こえない場合はそれも記録した。 記録した距離と角度を用いて調査路からの最短距離を求め、これを調査路からの距離とした。
密度は、調査する範囲にいる全体個数(群数)を調査面積で割った値となる。しかし、すべての個体(群)を発見できるとは限らないので、発見した個体数を発見確率で割ることでさらに補正した。
発見確率は、調査路からの距離で変わってくるはずであり、調査路から近ければ、発見確率は高くなり、逆に遠ければ、それは低くなる。発見確率は次のように仮定した。調査路上では1、直線的に減衰し、調査路からの距離が50mでゼロになる。
このような仮定に基づき調査路の両側50m(両側で100m)と考え、調査面積は、調査路の長さ14.3km×幅0.1km=1.43km2とした。
3日間、3回のラインセンサスでサルを9回、シカを50回観察した。シカについては、50回の観察で合計102頭を発見した。
密度推定は、50mで0を通る回帰直線を求め、0mにおける発見数が見落としのない発見数であるとした。
その結果、シカの発見確率は0.45、サルの発見確率は0.44となった。
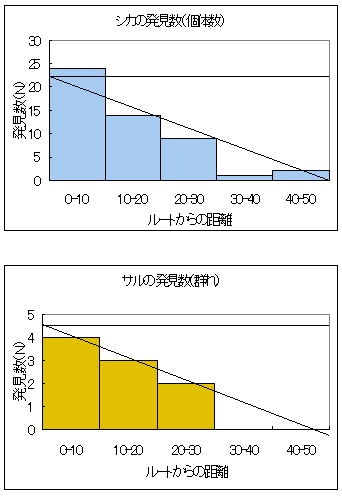
図3 ルートからの距離と発見数。ルートからサル(シカ)への距離が遠くなるに連れて、発見数は減少する。
密度=発見した個体数/発見確率/調査面積だから、
シカ個体密度=102/0.45/1.43=158頭/km2
サル群れ密度=9/0.44/1.43=14群/km2
となった。
シカ106頭(距離記録のない個体を含むため)の年齢・性別の構成を円グラフにしてみた。成体についてメスの方が多かった。これはメスがオスよりも寿命が長いためと考えられる。Adult sex ratio(成体オス/成体メス)は0.5となった。
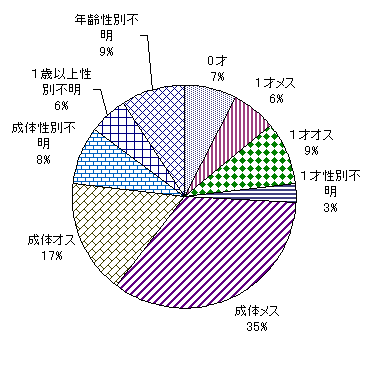
図4 シカの性・年齢構成
古道探しは密度調査に必要なことではないのだが、今回、密度調査にどう役立ったかについて考察する。
第一に、森の中を歩く練習ができた。最初は森の中で自分の位置を把握することは難しかったが、自分の歩いたルートや発見した遺物を地図上に記していくことで、密度調査時に必要な技術を身につけられた。また調査地域を予め何度か歩けたので川原地区の地形をおよそつかむことができた。
第二に、サル・シカの観察に慣れた。密度調査時、可能な限り各個体の性別及びおよその年齢を識別した。初めは、そもそもサル・シカを発見できなかったり、どこに注目したらいいのかわからなかったりしたが、古道探し中の観察を通して、識別に慣れ、発見しやすくなった。
第三に、使いやすい調査ルートを設定できた。私達受講生は山歩きに慣れてないため、調査中決めたルートから外れないように歩きながら、足元に気をつけ、且つサル・シカを発見していくのはとても大変なことだった。古道上はとても歩きやすかったので、発見に意識を集中することができ、調査の精度を上げることができただろう。このように、古道探しは密度調査の予備調査的な意味で役に立ったと思われる。
(1)サルの群れ数
推定群れ数は1km2あたり14群となった。これは明らかに大きな値である。まず疑われるのはカウントの重複である。50mルートと100mルートはわずか100~250m程しか離れておらず、サルも移動していくため、1つの群をそれぞれのルートがカウントして合わせて2群としてしまった可能性が高い。また、1つの群は広がりをもって存在しているため、同じ群内の2つの小集団を2群と数えてしまったことも考えられる。次に、カウントの重複がなかったとしても、サルの群れを点として扱い、調査路×両側100mという面積で割ったため密度が実際より高くなってしまったことも考えられる。サルの群れを点として扱う場合、群れの中心を代表する点とすれば特に問題はなさそうだが、今回は観察者が最初に発見した点を記録したため、実際より調査路のそばに存在するとされた群れが多くなり、発見確率の推定の精度が悪くなった可能性が高い。
後者は群れの大きさを推定するなど計算方法を変更する必要があるため改善が難しいが、前者は検討の余地があるのでカウントの重複がないか記録を再確認してみたい。
(2)シカの頭数
推定頭数は1km2あたり158頭となった。以前の川原地区のセンサスの結果は63-78頭(揚妻直樹他、調査年度1998-2001)である。
垂直距離の記録は発見回数毎であり、2頭以上の群れでは最も近い個体を代表とした。発見頭数をそのまま使うと精度が悪くなるかもしれないが、発見回数のみで計算すると実際の頭数を反映しないと思われるので、計算しなおした。その結果、サルの群れ数のように著しく大きい結果となった。先行研究は5年前のものであるので頭数が増えていてもおかしくないが、2倍以上増加したとは考えにくい。よって、シカもカウントの重複が疑われる。
今回の密度調査は特にサルについてあまり良い結果が得られなかった。その原因を考える。
(1)ルート設定
推定密度が大きくなってしまった主な理由にカウントの重複が考えられることから、定めたルート間の距離が近かったことが原因として考えられる。また、西部林道という舗装された道路を含んでいるが、森の中と環境がかなり違い、車や人の通行による攪乱がおきやすい。実際3回目のセンサス中、西部林道上で観光客の大集団とすれ違い、その後20分間サルもシカも見つからなかったことがあった。ルートを再検討すればより良い結果が得られるかもしれない。
(2)調査環境
3回のラインセンサスは行った時間帯が若干異なった。この違いでサルやシカの行動に特に変化はないそうなので、時間帯の設定には問題ないだろう。天候なども概ね一定だったので、調査環境の微細な違いが結果に大きな影響を与えたとは考えにくい。
(3)データ処理(計算方法)
発見確率について調査路の距離に対して直線的に発見確率が下がるとしたが、通常は減衰曲線を当てはめることが多いそうである。発見確率の推定が、密度推定に大きく反映されることから、発見確率の推定をもっと厳密に行った方が良かったかもしれない。また、予めカウントの重複を避けるための条件を厳しく設定するべきだっただろう。
2.カウントの重複について再吟味
カウントの重複について、コースの重複部分しか除外しなかった。値がおかしいからといって再計算するのは良くないことだが、カウントの重複の吟味は重要なことなので確認してみた。
考察で用いた先行研究と同じ条件をクリアしたもののみ使うこととする。
(1)発見箇所が、以前発見した場所及び動いた方向ではない
(2)発見箇所が近くても、年齢・性別が異なる
(3)以前発見した場所と300m以上離れている
上記の条件で確認してみたが、1回目のセンサスは地図記録がなかったのでできなかった。2,3回目は疑わしいものがいくつかあった。重複の可能性がある記録の一方が「性別年齢不明」などの場合、条件(2)に反するか微妙であるが重複とみなした。また、重複の可能性が高い2つの記録で発見頭数が異なる場合、発見頭数が多く年齢・性別をより識別できた方を採用した。精度の高い記録を使いたかったためだが、この採用方法はルート近くで発見した方に記録が偏る心配がある。吟味の結果、計2回のセンサスを見直して新たにサル1回、シカ2回を重複とみなした。
1回目のセンサスについて重複の再吟味をしていないのでまだ途中段階であるが、サルは、発見群れ数8群、発見確率59.8%で推定群れ数は1km2あたり9群となった。シカは、発見回数48回、発見頭数100頭になった。これを発見頭数を使用して計算すると、発見確率44.8%で推定頭数は1km2あたり156頭となった。
サルの推定群れ数は依然大きな値だが、カウントする群を1群減らしただけで値がだいぶ小さくなった。1回目のセンサスについて重複を確認すればさらに値が小さくなるかもしれない。群れ数をカウントするので発見数が一桁となり、1群をカウントするか否かで値が大きく変わるため、厳密に推定するには計算方法を変更する、センサス回数を増やすなどの根本的な改善が必要なようだ。
シカの推定群れ数は特に変わらなかった。大きな値の主な原因はカウントの重複ではない可能性がある。
3.シカの構成
成体についてメスの方が多かった。これはメスがオスよりも寿命が長いためと考えられる。Adult sex ratio(成体オス/成体メス)は0.5となった。これは先行研究の結果0.4‐1.0に含まれる。
1才についてはオスの方が多かった。1才の性比はおよそ1:1と思われるので、これは識別のしやすさの違いによるものと考えられる。1才のオスは小さな角があること、メスは角がないことで識別するため、メスの方が識別しにくい(識別に手間取る)。仮に1才性別不明が全てメスとすると性比はおよそ1:1になる。
京都大学野生動物研究センター > 屋久島フィールドワーク講座 > 第7回 2005年の活動-サル班-報告書
このページの問い合わせ先:京都大学野生動物研究センター 杉浦秀樹