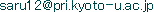| 京都大学霊長類研究所 > 2011年度 シンポジウム・研究会 > 第12回ニホンザル研究セミナー・要旨 | 最終更新日:2011年6月9日 |

| トップページ | プログラム | 要旨 | ポスター発表 | アクセス | 宿泊 | 食事 | その他 |
都市から森林に至る景観傾度と野生哺乳類
人間と野生動物の間には2つの方向性を持った軋轢が存在する。ひとつは、開発による自然環境の減少や狩猟といった人間活動による絶滅などの人間から野生動物への軋轢である。もうひとつは、農作物被害や病気の伝染などの野生動物から人間への軋轢である。人間と野生動物が共存していくためには、どちらも解消すべき問題である。本研究では、都市から森林に至る景観の変化に着目して、異なる景観で生じる軋轢を解消するために必要な情報を提供することを目的とした。具体的には、まず景観傾度と哺乳類の分布がどのように関係しているのか全体像を明らかにし、都市におけるノウサギと共存可能な景観設計と農地におけるイノシシによる農作物被害対策について検討する。
景観傾度と哺乳類の分布の関係を解析した結果、都市あるいは都市近郊の景観に多く生息している中・大型の在来哺乳類はノウサギとタヌキだけであった。特にノウサギは草食獣であり、猛禽類やテンなどの餌になることから、地域の生物多様性のために重要な種である。ノウサギは景観変化に敏感であるためハビタットが減少するとすぐにいなくなってしまうと考えられた。そのため、都市近郊におけるノウサギの保全には大きな森林パッチ(50ha以上)を維持することが重要である。
森林景観では、農作物への被害が多いニホンジカやニホンザル、イノシシが多く出現した。イノシシは分布が拡大しているため、将来の分布も考慮して被害対策を検討していく必要がある。すでにイノシシが分布している地域では、イノシシとの距離を保つような農地設計が必要である。具体的には、農地を林縁から離す、農地を集約し柵などの設置・管理を容易にする、林縁や休耕田の草を刈る、などが必要だと考えられた。
発表では上記の内容に加えて、現在取り組んでいる本州における大型哺乳類の将来の分布予測についても紹介する予定である。
都市近郊地域におけるニホンザルによる被害意識の実態
獣害問題の緩和には技術的な課題だけでなく、被害住民の認識や考え方を考慮することが重要である。従来、ニホンザルによる被害に対する住民意識は主に農村部における研究であり、都市部やその近郊域における調査事例は少ない。都市近郊域では農村部でみられるような過疎・高齢化による人口減少といった社会問題は少ないが、組織的活動が困難になるといった問題が指摘されており、被害対策を実施するうえで不具合が生じることが考えられる。本研究は、90年代から被害が報告されており深刻化している山梨県富士吉田市と富士河口湖町において、住民意識と被害リスクとの関係を検討した。具体的には、住民意識の把握方法として林縁から300m以内の住宅へナンバリングを施した質問票を配布、回収した。被害リスクの評価には加害群のラジオテレメトリー調査結果のポイントの密度推定量を用い、その推定には固定カーネル法を実施した。住民意識と被害リスクの空間分布の比較検討を容易にするため、住民意識は質問項目ごとにIDWによる空間補間を実施した。さらに、被害リスクが住民意識に及ぼす因果関係を共分散構造分析によりモデル化した。その結果、加害リスクと住民意識はおおよそ空間的に一致するが、一部加害群以外の影響があり、対策の集団化に関しては被害リスクの低い地区では地区内の考え方が一致しないことが判明した。被害リスクは住民の被害意識に影響があり、サルに対する悪い印象や捕獲への要望、地域一体となった対策の必要性といった住民意識は被害意識に影響をうけるモデルが採択された。以上のことから、対象地域では被害意識に差があり、そのことが対策意欲の一体感を欠落させるため被害対策が困難となっている状況が推察された。
冷温帯林におけるニホンザル野生群の冬期森林利用に関する空間的評価
北東北に分布するニホンザルは、過去の乱獲により、その生息地が孤立・分断化した。その中でも、地域個体群は、北東北最大の生息分布域を示していることから、ソース個体群として機能することが期待されている。しかしその生息地内には、スギを始めとする針葉樹人工林が広く分布している。針葉樹人工林はニホンザルにとって、餌資源が少なく低質な植生タイプと考えられてきたが、これは暖帯林での研究事例から指摘されたものであり、冷温帯林における同様の研究事例は乏しい。そこで本研究では、北東北のニホンザル、とりわけ冷温帯多雪地である青森県白神山地に生息するニホンザルの生息地としての針葉樹人工林の質について、①ニホンザルの冬期採食地選択、②針葉樹人工林におけるニホンザルの冬期の餌資源量、の二つの観点から評価した。
① ニホンザルの冬期採食地選択に関する空間評価 本研究では、ニホンザル野生群の直接観察から得られたデータを基に、本種の採食適地の推定を試みた。ニホンザルの採食個体が観察された地点を記録し、地形や植生、土地条件等を環境変数として、在データのみで解析が出来るENFA(ecological-niche factor analysis)を用いて解析した。 その結果、本種の採食適地は、低標高域で林道に近い、南斜面の若齢針葉樹人工林に偏って分布していることが示され、またそれぞれの環境に対する適地の幅は小さかった。このことから冷温帯林における若齢針葉樹人工林は、冬期のニホンザルの採食地として機能することが明らかになった。
② 針葉樹人工林におけるニホンザルの冬期餌資源量評価 上記の結果を受け、林齢20年生から60年生までのスギ人工林およびブナ一次林において、ニホンザルの冬期餌樹木種の資源量とその多様度を評価した。その結果、餌樹木資源量およびその多様度は、林齢20年生から40年生にかけて減少し、林齢40年生の林分で最少となった。またサルの冬期餌樹木本数は、スギの胸高断面積合計が少なく、傾斜のある林分において増加することが示された。40年生の林分で餌樹木資源量とその多様度が最少になったのは、林齢増加にともなうスギの林冠閉鎖により、林内への日射量が減少したためだと考えられ、林冠閉鎖前後の間伐がスギ人工林内に本種の餌資源を維持する上で重要であることが示唆された。また傾斜のある林分において餌樹木本数が増加することについては、林内への日射量が影響していると考えられた。 一方、ブナ一次林における餌資源評価の結果、餌樹木の資源量はブナ一次林の方がすべての林齢のスギ人工林よりも多かったが、餌樹木の本数密度や種多様度は、ブナ一次林の方がすべてのスギ人工林よりも低かった。このことから当該地域では、ニホンザルの生息地としてのスギ人工林は、必ずしも低質な植生タイプではないことが明らかとなった。本研究の結論は暖帯林の事例と異なっていたが,その要因として、植栽木に対する雪害が挙げられた。本調査地では雪害が発生することによってスギの立木本数が暖帯林よりも少なく、林冠閉鎖の起こる林齢が暖温帯林と比較して遅くなることが、当該種の餌資源量等に影響していると考えられた。
本研究では植栽木に対する雪害が起こるために、ニホンザルの生息地としての針葉樹人工林は必ずしも低質ではないと結論付けられたが、雪害は木材生産を目的とする人工林に対し損害である。林業採算性の低下により、間伐遅れの林分が増加している昨今では、現存する針葉樹人工林をすべて適切に管理することは難しく、林分によっては粗放的管理を行う選択肢も必要である。植栽木に対する雪害は平坦地では起こりにくいことが報告されていることから、当該地域では傾斜地にある針葉樹人工林を粗放的に管理し、平坦地では木材生産を目的とする人工林として適切な時期に間伐を行うことにより、「木材生産を目的とする人工林」と「ニホンザルの生息地保全」の両立が可能になると考えられた。
Epidemiology of nematode parasite infection among wild Japanese macaques: heterogeneity in the external and internal environments
One of the fundamental characteristics of parasite infection dynamics is that parasite distributions are typically aggregated across host populations; most of the hosts carry few parasites while few hosts carry most of the parasites. Understanding why such variation across hosts exists continues to be an active area of research in infectious disease epidemiology. My research is focused on investigating patterns of infection across hosts under natural conditions, using Japanese macaques on Yakushima (Macaca fuscata yakui) and their gastrointestinal nematode parasites as a single host-multiple parasite model study system. Japanese macaques across their range are infected by a total of 5 species of nematode parasite, but only the population on Yakushima is infected by all of them (Gotoh 2000). From October 2007 to August 2009 I observed and collected fecal samples from a group of macaques (“umi”) inhabiting the Kawahara area of the Seibu-rindo. Wherever possible, I collected 2 fecal samples (N=707) per individual (N=64) per month (N=16) during 4 non-overlapping seasons (N=8), storing approx. 1 g of feces in 2 ml plastic cryo-tubes containing approx. 0.75 ml 10% buffered formalin solution, and processing all samples at the Kyoto University Primate Research Institute via a modified formalin-ether sedimentation protocol (Young et al. 1979). The results show clearly that all parasite species are characterized by aggregated distributions across the host study group, as predicted. Linear and generalized linear mixed-effects models show that infections by all 5 nematode species are seasonal (dependent upon conditions of the external environment), with the majority exhibiting peaks of prevalence (the proportion of hosts infected) and fecal egg output (eggs per gram of feces (EPG); the mean number of eggs shed in the feces per individual) during spring or summer. In addition, host traits (i.e. conditions of the internal environment) such as age, sex, reproductive seasonality, dominance rank, grooming behavior and social network position all affect transmission of these parasitic nematodes to varying degrees. I discuss these results in relation to the underlying mechanisms of transmission that they suggest, and what they can tell us about the co-evolutionary histories of these natural enemy species.
ニホンザル雄の集団からの一時離脱行動: 採食、繁殖戦略の観点から
ニホンザル雄の一時孤立行動を明らかにするため、二個体同時追跡を非交尾期に屋久島で行った。また採食戦略上の意義を検討するため集団内外の採食行動を比較した。オスと集団の距離は全観察時間(260時間)の27.5%で100m以上であり、最大で632m離れた。100m以上離れた場合の継続時間は平均で68分であった。オスは孤立している時に、そうでないときよりも有意に多くの時間を採食に充てていた。孤立した時には一つのパッチに滞在する時間が増加し、利用するパッチサイズも大きくなる傾向があった。これは雄が孤立することによって集団内採食競合を回避している可能性を示唆している。またオスが孤立した時の採食速度は、そうでないときに比べて減少していた。集団内で採食中のオスは、他個体からの攻撃によって採食を中断される可能性や集団の移動に追従する必要性から、採食速度を増大させているのかもしれない。また低順位のオスほど、集団から孤立する頻度と時間が大きかった。低順位のオスは集団内での採食上の不利を、一時孤立行動によって補償する戦略を取っているのかもしれない。
遺伝子・細胞・個体レベルからみたニホンザルの苦味感覚
【背景と目的】野生下での動物種において、地域によって採食品目が異なる場合や、個体によって食物に対する嗜好性が異なる場合がしばしば見られる。このような現象の原因として、その食物を認識する味覚器の反応性に差が生じていることが推測される。つまり、味覚器で呈味物質と結合する味覚受容体に変異が生じ味覚器の感受性が多様化する。それにともなって食物に対する行動が多様化し、採食品目に差が生じるという仮説である。味覚の中でも苦味感覚は、採食品目に含まれる生理活性物質や毒性物質を検出するため、苦味受容体遺伝子TAS2Rは環境の植生の違いや個体の代謝能に応じて進化的に柔軟な変化を示す可能性がある。霊長類ではTAS2Rの遺伝子変異と苦味感受性変異との関係が報告されている。例としてTAS2R38に変異が生じたヒトおよびチンパンジーは人工苦味物質PTC (phenylthiocarbamide) の感受性が低いことが報告されている。しかし、日本固有種であり各種実験に有用なニホンザルを含む他の霊長類種では類似の研究は皆無である。そこで本研究は以下の項目を目的としておこなった。ニホンザルのいろいろな地域集団をもちいてTAS2R38の配列解析をおこなう。変異の特定と集団の特性を把握するとともに、細胞および個体レベルのPTCに対する反応性を明らかにする。最終的に、これらの実験データに基づいて、野生下におけるニホンザルの採食行動と遺伝子変異との関係を探る。
【遺伝子解析】はじめに、ニホンザル409個体およびアカゲザル55個体のTAS2R38の多型解析を行った。その結果、ニホンザルにおいてTAS2R38遺伝子中に12か所の塩基置換が同定され、13種類のハプロタイプが存在していた。このうち、紀伊半島の一部の集団のみから開始コドンに変異をもつ受容体の機能を失ったと考えられるハプロタイプKが、集団中の遺伝子頻度29%の割合で同定された。
【機能解析】この変異について、細胞レベルでの反応性を明らかにするために、培養細胞を用いた機能解析を行った。その結果、通常の開始コドンをもつハプロタイプAとBではPTCに対して反応を示したが、開始コドンに変異をもつハプロタイプKでは反応を示さなかった。この結果から、細胞レベルにおいてハプロタイプKの遺伝子型をもつ受容体はPTCに対する反応性を失っていることが明らかになった。
【行動実験】さらに、このハプロタイプKをもつ個体のPTCに対する反応を明らかにするためにリンゴ片を用いた給餌実験、二瓶法による給水実験を行った。どちらの結果からも、ハプロタイプKのホモ個体はその他の遺伝子型の個体に比べて有意にPTC受容能力が低いことが明らかになった。
【考察】以上の結果、特定の地域由来のニホンザルにおいてPTC感受性の低い個体の存在を同定した。ヒトとチンパンジーにおけるTAS2R38遺伝子変異は2種が分岐したのちに独立に起こったことが報告されている。さらに、本研究の結果からニホンザルのPTC感受性変異はニホンザルとアカゲザルが分岐した後、ヒトやチンパンジーとは独立に生じていることが推測された。このことから、霊長類の進化過程で長い間保存されてきたTAS2R38の機能は、種分化後、独立に3種でそれぞれ遺伝子変異が起こり感受性に個体差が生じていることが考えられる。 また、PTCを受容するTAS2R38は天然苦味物質としてアブラナ科の植物に含まれるグルコシノレートや、柑橘類に含まれるリモニンを受容する。この変異型の遺伝子を持つ個体は、(1)これらの食物に含まれる苦味を感じないことで採食品目が増えたこと、あるいは、(2)この地域にはこれらの苦味を含む食物が存在せず、苦味を感じなくても淘汰されなかったことが示唆される。今後、多角的なアプローチが必要ではあるが、現在のデータからは、これらの要因によってTAS2R38のハプロタイプKが集団内に広がり、維持されてきたことが推測される。本研究でニホンザルにおいて発見した上記の結果は、霊長類の苦味感覚を理解する上で、生態学的、進化的な側面から大きな役割を果たすことが期待される。
勝山ニホンザル集団における毛づくろいの駆け引きと互恵性
霊長類が頻繁に行う毛づくろいは、重要な社会行動である。彼らは、お互いに毛づくろいを交換し、互恵的に毛づくろいのやり取りを行っていると言われている。最近の研究では、その場での短期的な交換と、何度か交渉を重ねることによる長期的な交換のうち、どちらの交換が、毛づくろいの互恵性に強く影響しているのかが、議論の対象となっている。Muroyama (1991)の研究では、ニホンザルが催促行動を用いて、その場で短期的に毛づくろいを交換していることが示唆されている。本研究では、ニホンザルメスの毛づくろいにおいて、催促行動を用いた短期的な交換が、個体間で行われた毛づくろいの時間を均等にし、毛づくろいの互恵性を高めているのかを検討した。 勝山ニホンザル集団(岡山県真庭市)における4歳齢以上のメス全56頭の中から、14頭を対象個体として選出し、個体追跡法による1セッション30分の連続観察を行い、毛づくろいや催促行動を記録した。観察期間は、2009年10月から2010年9月までの約1年間で、総観察時間は220時間であった。メスの個体間関係を、近接率と血縁関係に基づいて、血縁個体間、親密な非血縁個体間、親密でない非血縁個体間の3つに分けて分析を行った。 ニホンザルメスが、相手に毛づくろいした後に、催促を行うことで、相手からお返しの毛づくろいを受けているのかを検討した。どの個体間関係でも、自分が毛づくろいした後で、相手に毛づくろいの催促をした場合には、催促をしなかった場合よりも、お返しの毛づくろいを受けることが多くなっていた。次に、このような催促を用いたその場での毛づくろいの交換は、メス間で1年間に行われる長期的な毛づくろいの互恵性に、影響を与えているのかを検討した。検討にあたり、それぞれの個体間関係を、毛づくろい後の催促率が高い群と低い群とに2分して分析を行った。血縁個体間と親密な非血縁個体間では、毛づくろい後に頻繁に催促している個体間でも頻繁には催促をしていない個体間でも、長期的な互恵性は同程度であった。一方、親密でない非血縁個体間のうち、毛づくろい後に頻繁には催促をしない個体間では、長期的な毛づくろいの互恵性は低くなっていた。最後に、対象個体が行った催促行動のうち、毛づくろい後に行われた催促行動を除いて、催促の成功率を調べた。親密でない非血縁個体間では、毛づくろい後以外の場面で行われた催促の成功率が低くなっていた。 以上のことから、毛づくろい後の催促行動は、その場での短期的な交換を促進する働きがあることが示された。また、毛づくろいの互恵性は、血縁個体間や親密な非血縁個体間では、長期的な交換によって高められ、親密でない非血縁個体間では、短期的な交換によって高められていることが明らかとなった。
景観構造の違いがニホンザルの農地侵入に与える影響
景観の異質性は、様々な生態学的プロセスを生み出す。動物の生息地における、森林や農地といった景観構造の空間パターンを明らかにする事は、野生動物の管理において重要な課題である。本研究では、新潟県新発田市に生息する互いに隣接する2つの野生サル群と生息地の景観構造に着目した。群れの農地への侵入に対する違いを明らかにし、生息地の面積、形状、空間的配置の違いが、群れ間の差に対し、どのように影響するかを評価した。
ラジオテレメトリーによる調査の結果、遊動域は大槻群の方が大きく、その中に含まれる農地や人工物の割合も高かった。一方、遊動域内に含まれる森林の割合は米倉群の方が高かった。また、各パッチの景観指標を算出した結果、米倉群と大槻群の生息地における景観構造は大きく異なっていた。一般化線形混合モデルにより、農地侵入と環境要因との関係を明らかにした結果、両群れともに、林縁からの距離が重要な因子であった。また、道路からの距離もリスク因子となっていたが、防護柵からの距離に関しては群れ間で違った。米倉群では、防護柵からの距離はリスク因子として寄与していたが、大槻群ではリスク因子にはならなかった。大槻群の生息地は、林縁が複雑な形をしている。また、農地が連続的に配置されているため、農地への進出が容易になり、人慣れが進むことが考えられる。つまり、群れの農地侵入に対し、生息地の景観構造が影響する事が推察された。
ニホンザルの管理を目的とした堅果類のマッピング
本論の調査地のある新潟県新発田市では、ニホンザル(以下サル)によって年間1000万円超の農作物被害が発生しており、現在対策の一つとして追い上げが注目されている。追い上げとは、農地に侵入したサルを追い払うだけでなく、目標地点まで積極的に追い立てる行為を指す。追い上げを行う際は、サルが再び人里に下りてこないように、目標地点に充分な餌資源が存在する必要がある。そこで本論では、サル生息域周辺山中の餌資源を把握するため、高分解能衛星画像(IKONOS衛星:分解能1m)からサルの食糧となる堅果類のマッピングを試みた。
分類では堅果類の詳細な分布を把握するため、植生部を堅果類、針葉樹林、林種不確定の3クラスに区分した後、林種不確定クラスの下に4つの下位クラスを設けた。その結果、調査エリアから6割の精度で堅果類を抽出できた。しかし本論では現地調査点が少ないため、トレーニングサンプルの精度低下や、精度検証に用いるテストサンプルに偏りがある可能性が高い。そのため、調査エリア全体の精度を捉えるには不十分であると考えられる。今後は、堅果類の分布情報に加えて、堅果量や位置条件(標高、傾斜角)といったサルの生息適地としての条件を考慮した追い上げ候補地の抽出を行う予定である。
動物専用周波数帯を利用したニホンザルのリアルタイムモニタリングシステム
知能の高いニホンザル(Macaca fuscata)から農作物を守るためには、群れの行動を常にモニタリングし、集落に入る前に予防的な追い払いを行う必要がある。サルの群れを追い続ける労働力を減じるため、複数の固定アンテナから受信した電波強度からサルの位置を3点法で定位し、得られた位置データをWeb上にリアルタイムで表示するシステムを開発し、その精度の検証を行った。
調査は、新潟県中魚沼郡津南町と長野県下水内郡栄村の境界域を流れる志久見川沿いにある河岸段丘に位置する集落、畑作地で行った。システムの精度を検証する方法として、調査地に5カ所の固定アンテナを設置し、各アンテナから半径500 m以内の範囲に58箇所の調査地点を設置した。国内で認可されている動物専用周波数帯を利用したVHF電波発信器(サーキットデザイン社 LT-01)を0.5 mの高さで約2分間保持し、その位置をGPS(Trimble社 GPS Pathfinder SB)とシステムで同時に定位し、2点の距離を計測した。
その結果、5カ所の固定アンテナの内側の地点(254.4±293.5 m)にくらべ、外側の地点(528.6±340.4 m)では、システムとGPSによって定位された位置の差が大きくなった。アンテナの内側では、最寄りの2点の固定アンテナの直線と地点のなす角度が10o以下の範囲やアンテナと地点の間に遮蔽物や土地の高低差がある場合は定位精度が低かった。一方、アンテナの外側であっても、地点とアンテナ間に遮蔽物がなく、最寄りの2点の固定アンテナの直線と地点のなす角度が30o以上の地点では定位精度が高かった。
ワカモノ期ニホンザルにおける母娘関係と成体との毛づくろい関係の形成
ワカモノ期は、未成体同士から成体同士の関係への移行期である。ワカメスの成体との関係形成に影響する要因のひとつとして、母の存在が挙げられる。今回の研究では、ニホンザル(Macaca fuscata)のワカモノ期の社会的発達の過程を明らかにすることを目的とし、母との相互交渉の少なさが、成体メスとの関係形成を促進する、という仮説を検討した。
嵐山ニホンザルE集団の6-9歳齢の未経産メス12頭を対象とし、母との相互交渉(毛づくろい交渉、近接)と成体メス(非血縁、10歳齢以上)との毛づくろい交渉を記録した。年齢、順位(高・低)、母との相互交渉の生起率を説明変数、成体メスとの毛づくろい交渉の生起率と毛づくろい相手数を目的変数とする重回帰分析を行った。
成体メスから受けた毛づくろい生起率は、母に対して行った毛づくろい生起率と近接率が有意な説明力を持っていた。さらに、毛づくろいを一度でも受けたことのある成体メスの数は、母から受けた毛づくろい生起率と母との近接率がどちらも有意な負の説明力を持っていた。つまり、毛づくろいを受けることが少なく、毛づくろい以外で母との近接が少ないワカメスほど、多くの成体メスから多くの毛づくろいを受けていた。ワカメスが将来的に非血縁個体と互恵的な毛づくろい関係を形成する上で、母との密接さが影響する可能性が示唆された。
農地を利用するようになったニホンザル群の群落利用
ニホンザルによる農業被害(猿害)が問題になり、駆除による問題解決がおこなわれている。しかし、そもそも猿害が発生した原因のひとつは、人間によって生息地の環境が改変されたことにある。生活環境(具体的には森林)が農地になれば、サルにとって栄養価の高い食物である農作物が集中的に供給されることになる。このことは、サルの群落利用や食性に影響を与えずにはいられないであろう。そこで本研究では、農地に依存的になった群れ(加害群)と、野生状態に近い群れ(自然群)の群落利用を比較し、その違いを把握することを目的とした。
調査は神奈川県丹沢地域に属する2群を対象に、ラジオテレメトリ法から得た群れの位置と、GIS上の植生図を用いることで、群落の選択指数をManlyの方法で検討した。
群落選択性では、2群ともに広葉樹林を有意に選択していた。季節ごとには、「自然群」は秋に広葉樹林を選択し、草地と農地と市街地を忌避した。一方、「加害群」は、どの季節でも市街地を忌避した。また、どの季節においても農地の選択指数は高くなっていたが、秋には広葉樹林の値の方が高くなった。「自然群」で夏の草地や秋の広葉樹林の利用が増えたことは、採食物の利用可能な場所と関係していると考えられる。これに対して、「加害群」は農地を利用していたことから、「自然群」の草地の役割が農地にとって代わったと考えた。
人間による生息地環境の改変によりサルに影響を与えた上で、さらに対策として駆除を採用することは、サルに対してさらなる悪影響を与えることになる。保全という立場からは駆除に頼らない猿害対策が望ましいが、本研究のような生態学的アプローチから、「加害群」の生活に関する情報を蓄積することによって、駆除に頼らない猿害対策に応用することを期待したい。
京都大学霊長類研究所 > 2011年度 シンポジウム・研究会 > 第12回ニホンザル研究セミナー・要旨
このページの問い合わせ先:京都大学霊長類研究所 半谷吾郎
E-mail: