直接見られない野生のマレーバクの行動を研究できるか?
彼らの「塩場」の利用を手掛かりに
田和優子
ずんぐりした体型でのんびり動くバクは、実は約二千万年前からその姿をほとんど変えていない生きた化石です。人類の歴史でいうと、二千万年前はヒト科とテナガザル科が分岐したころです。バクはあまり研究されておらず、その生態は謎に包まれています。私の研究対象であるマレーバクはうっそうとした熱帯雨林で夜間に活動するため、直接彼らを観察するのは非常に難しいのです。そのため、彼らが野生下でどのように行動しているのか、ほとんど分かっていません。
私は何とかして野生のマレーバクの行動を観察しようと、「塩場」に着目することにしました。塩場とは、ミネラルを多く含む土や水が地面に出ているところで、森の中に点在しています。草食動物は、餌の植物に不足しがちなミネラルを摂取するために、ここに集まってきます。私は、5ヶ所の塩場に自動撮影カメラを設置し、そこを利用しに来たマレーバクを撮影し動画を集めて、それをパソコンで再生し、「バク同士はどのように接しているのか」に着目して彼らの行動を観察しています。
動画を解析したところ、マレーバクは約2日に1回、観察しているいずれかの塩場を訪れていました。ふつう、森の中のけもの道にカメラを設置してもこれほど頻繁に撮影されることはありません。撮影されたバクの耳先の切れ込みや額の傷を手がかりに個体識別をしてみると、ある塩場には8個体ものマレーバクが利用しに来ていることが分かりました。しかし、塩場は共通の資源であるにもかかわらず、他個体と仲良く並んで水をなめる、なんてことは一切ありません。それどころか他個体との遭遇を避けており、マレーバク同士はかなり排他的な関係にあることがうかがえました。ただし、カップルだけは例外で、一緒に塩場の水をなめつつお互いに鼻先でちょんちょんと触れ合い、相手に声をかけるように「ピィ~」「クカッ」と鳴きかけてから連れ立って塩場から出ていくという、仲むつまじい姿を見せてくれます。バクはこれまで単独性と言われてきたので予想外でしたが、カップルが共に行動する様子は実際に何度も撮影されています。バク同士は普段、直接顔を合わせることすらないけれども、カップル間では触れたり鳴いたり…。このように、あまり研究されず謎に包まれていた野生のマレーバク同士の関係やコミュニケーションについて、カメラを使った観察によって少しずつ明らかになってきています。
 塩場。特に草食動物がミネラルを多く含む水を飲みに来る。
塩場。特に草食動物がミネラルを多く含む水を飲みに来る。

共に塩場の水を飲むカップル
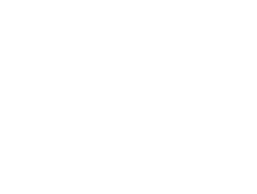


ボートでダム湖を渡って調査ポイントに向かう。

ガイドと荷物持ちをしてくれる人を、日雇い。
このページをシェアする
